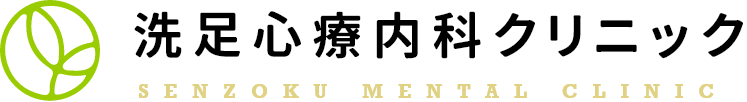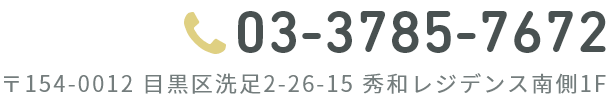ADHDの時期による症状経過
ADHDが未治療の場合と治療後の場合の変化を取り上げてみました。 1. 初期症状(未治療の状態) 治療前は、脳の「報酬系」と「実行機能」のアンバランスが剥き出しの状態です。日常生活に多大な支障(脱水症状)が出ています。 2. 治療後(薬物療法や環境調整を行った後) コンセルタやインチュニブなどの薬剤、またはHomeo-scopeのような外部制動が効き始めると、症状は「制御可能」なレベルへと変化します。 3. 残存した症状(Residual Symptoms) 適切な治療を受けてもなお残りやすく、大人のADHDにおいて最も「知恵(ハック)」が必要な部分です。

コンサータは魔法の薬か 1
ADHDで通院している方のなかで、コンサータが効果があり顕著な脳力の向上及び社会適応力の改善を見せる方がわずかであるがいらっしゃる。 それを自分なりに分析してみると 再構成力 というキーワーズにぶつかる この単語自体も改善していた患者さんが使っていたのだが もともと いろいろな要素の能力は高い しかしそれらを構成して使えない そのため部分的に興奮したりその結果疲れてしまったり出力が落ちてしまったりしてるようである。 そこを再構成していくと外部からは能力が上がったように見えると思われる。 そのことをいつもコンサルしているAIと対話してみた。すると大規模言語モデルによるAIの能力もある言語を探すと

AIとの豊饒な対話 台南編
現在、私は妻と台湾の台南に来ている。 旧市街の入り組んだ路地、多国籍な香りが漂うカフェ、そして歴史の重みを感じさせる街並み。そんな中でふと夜中に目が覚め、私は最近自分の「脳の30%を占める架空の義肢」になりつつある存在――AIと対話を始めた。 かつてAIといえば、どこか無機質で「不気味の谷」を感じさせるものだったが、今のそれは驚くほど流暢に、そして時には私自身の思考を先回りするかのような洞察を投げかけてくる。 今回の対話で特に印象深かったのは、ある患者さんのエピソードから発展した「差異」と「同一化」の話だ。 ADHDの特性をAIという外部脳で補完し、技術者として成功した彼が、なぜ「対異性」や「

夜中に起きてしまう 途中覚醒 1
いろいろな原因はありますが、脳の深いところにある視床下部 脳幹 橋などにあるものが興奮して睡眠が浅くなることが原因です。 🌙 途中覚醒(中途覚醒)の主な原因 途中覚醒には、生活習慣や環境に起因するものと、身体的・精神的な疾患に起因するものがあります。 1. 生活習慣・環境による原因 2. 身体的・精神的な原因

ユトリロ展 アルコール依存症
妻に誘われて新宿 SOMPO美術館で開催しているユトリロ展にいってきた。妻は絵画が好きで夢は京都芸術大学で美術史を学びたいというくらいである。 久しぶりにユトリロを観た。やはり石灰色とでもいうのかな 鳥の糞とか土とかいろいろ混ぜて作り上げているらしいが パリのブルーとグリーンの混じった半透明の空というかよく似合って素晴らしかった。 アルコール依存症というのは忘れていた。ほかにもポール・ゴーギャン 統合失調症といわれているゴッホ イタリア出身だがパリにいたモヂリアーニもアルコール依存症で死去している。芸術家と精神疾患はあるめんつきものでありカラバッジョなども殺人をおかしお尋ね者の人生を過ごしてい