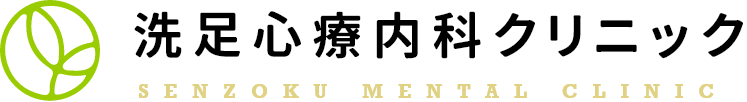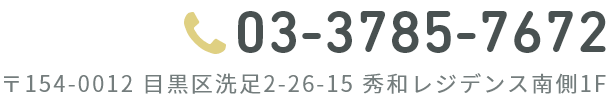精神科薬を飲むときの心得

精神科薬を服用するときに、意外に出てくるのがプラシーボ効果です。たいがいは患者さんは困って来院されて処方をされますが、服用するときにこれは効くだろう 効いたらよいなとおもって服用します。または医師によっては効果がありますよと暗示をかける先生もいるかもしれません。すると精神科薬は正のプラシーボ効果を発揮するといってよいでしょう。ところがマイナスのプラシーボ効果が出ることもあります。それはいやいや飲む または副作用や依存が怖くて摂取するときもその気分でマイナスの効果が出てくるかもしれません。
もう一つはこの薬は絶対効果があるはずだと思い込むこともよくありません。すると精神科薬は即効性がそうあるはずではなくまた何回か飲むうちに効果が薄れていくこともあり また標的症状に効果のないこともあるので効果がないという焦燥感、ひどいと怒りが出ることさえあります。これはマイナスのプラシーボ効果といってもよいでしょう。当院でやっている治験のばあい例えば抗うつ薬を例にとると時間軸を横軸 効果を縦軸にしたグラフを作るのですが 実薬とプラシーボの曲線の差は実はかなり似たものとなっています。
コンサータなどはやはりADHDに効果があるという情報がいきわたっているので初めから効果があるはずだという患者さんも多くみられます。むかしはリタリンといっていましたが、その影響なのか効果が薄れていくにしたがい大量摂取となるという典型的な依存形成を見せることがありました。現在ではそれを防ぐシステムや剤型になっています。

そこで患者さんにはどういった心構えで服薬したらよいかを医師の立場から申しますと、この薬は効くのか聞かないかわからないがまず経験として飲んでみようとニュートラルな気持ちで服用するのが一番良いと思われます。効果が歩かないか 副作用はそうしたバイアスのない状態で判断していただくのが最適かと考えます。